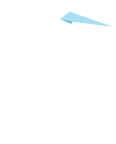本年度の事業別計画は以下の通りです。
記号説明(事業担当委員会)
-
教育
IT公益推進委員会 教育部会
-
広報
IT公益推進委員会 広報部会
-
IT
IT公益推進委員会 IT推進部会
-
企画
企画運営委員会
-
社会
社会貢献委員会
-
会員
会員増強委員会
-
公益
公益総務委員会
-
ハト
ハートフルファンデーション委員会
Ⅰ.教育啓発・情報提供活動事業(公益目的事業1)
-
1. 広報誌「Present」の電子化推進 教育
昨今、書籍や雑誌も電子化の進展に対応し、広報誌「Present」も4月号より紙媒体を廃止し、完全電子に移行する。
広報誌「Present」をまだ紙媒体、冊子で配布している会社があるため、印刷や配送に大きな経費が計上されているが、完全電子化により節減したい。これにより、節減できた経費は再分配を行い、コンテンツや機能のさらなる充実を図っていきたい。広報部会やIT推進部会とも連携し、ITを駆使した広報活動を取り入れることができるようにする。また、広報部会、IT推進部会とも連携して教育事業にて展開できることを推進する。 -
2. 地方協会における一般消費者の方々の参加を募る講演会、研修会、セミナーなどの実施 教育
- ① 公益性向上を図り、より広く一般消費者の方々に参加していただくため講師に芸能人や著名人を招聘し一般消費者の集客率を上げるとともに、講演会にメディアの取材を入れることによりJAIFAの公益事業のPRを図る。
- ② 地方協会研修会への本部役員講師を派遣する。
- ③ ホームページの活用により、地方協会セミナー情報を管理するなどコンテンツの充実を図る。また、開催報告の徹底も図る。
-
3. 生命保険普及活動資料やツールの制作活用 教育
下記資料等の制作についても積極的に推進し、公益社団法人として果たせる役割としての、教育広報への取り組み強化を推進する。
- ① 札幌協会が企画立案し制作している、税金・年金・医療・暮らし等の情報を盛り込んだ「暮らしのあれこれ豆知識」冊子が好評を得ており、他の地方協会にも広げていく。
- ② 各地の講演会やセミナー等で、過去これまでに開催された年次大会ダイジェストDVDを上映することにより、公益活動のPRや、香川年次大会の集客に繋げていく。
-
4. JAIFA年次統一セミナーの教育事業としての役割 教育
企画運営委員会が公益事業活動の位置づけのもと、広く一般消費者の方々にも参加していただくためのセミナーとすべく準備を行っている。教育部会としては、セミナーを継続担当し充実を図る。「教育啓発・情報提供」事業に位置づけ、具体的には香川年次大会企画「お客様からの感謝の声」を公益事業の一環とする。
- ① 会員以外の一般消費者の方々の参加率の向上を図り、会員と一般消費者の方々が、生命保険制度の正しい知識と有効性を確認し、生命保険制度の健全な普及に寄与する。
- ② セミナーのプログラムは、生命保険に関する教育啓発の一環で、一般消費者の方々も含めた参加者がともに共感しあえる場として、契約者の体験を通して生命保険の重要性を訴える内容を計画する。
-
5. LINE公式アカウント登録の推進 IT
ホームページへのアクセス数アップを目的に、LINE公式アカウントを開設。
お友だち登録してもらい、登録先へ定期的にアップデート内容を配信することで、ホームページへのコンタクト機会を増やす。LINEを通じて手軽にアクセスできるようにすることで、大幅なアクセス数の改善を目指す。登録目標10,000件(2024年10月時点3,500件)を目指す。 -
6. ホームページアクセス数向上へ向けた取り組みの継続 IT
2024年10月より、LINE定期配信を月に1回から2回へと変更。具体的には、月初の広報誌「Present」の配信に加え、JAIFA学習帖の人気ランキングの配信を追加。月に2回の定期配信に加え、スポットで、各委員会の情報配信も行うことで、LINEアカウント経由での簡便なアクセスを周知し、定着させ、アクセス数増へ繋げていく。
あわせて、各地方協会でのホームページの積極的な活用を推進する。
定期的な勉強会を通じて、活用をサポートしていく。
既に、広報誌「Present」誌面記事も、バックナンバーを含めホームページ内にて閲覧できる仕様となっており、教育部会・広報部会とも協力しながら、ホームページからの閲覧を推奨することで、ペーパレス化の推進にも繋げていく。
令和6年度に、会員数の約5割となる月20,000件のアクセス数を達成したことを受け、令和7年度は、会員数の約75%の月30,000件を目標とする。 -
7. 「JAIFA学習帖」の内容リニューアルと定期配信を通じたアクセス増への取り組み IT
会員専用学習プログラム「JAIFA学習帖」の利用率は低調で推移。
アクセスパスワードを簡易化は実施済み。
NISAやiDeCoなどの資産運用コンテンツの追加も実施済み。
教育部会・広報部会とも連携しながら、より実践的で魅力的な内容のコンテンツへの見直しも継続的に行う。
LINEによる、月に一度の人気ランキング配信を継続し、認知度を高め、容易にアクセスできる環境を整えることで、トップページ閲覧数で、月6,000件を目標とする。 -
8. 定時総会における、議案書・委任状発送、委任状回収業務の電子化の検討 IT
毎年の定時総会における、議案書・委任状発送、委任状回収業務に関し、紙媒体の委任状回収、本部への発送、集計のスケジュールがタイトで、運用が繁雑となっていることを受け、諸手続きの電子化を検討していく。
-
9. JAIFA公式LINE・会員専用学習プログラム「JAIFA学習帖」の充実 公益
IT推進部会と教育部会が横連携しているJAIFA公式LINEとホームページ上の会員専用サイト「JAIFA学習帖」が、更に充実した内容となるよう必要な予算を確保する。このサイトを活用し会員の知識が向上することで、一般消費者への質の高い情報を提供していく。また、必要に応じて運用の見直しを図る。
-
10. 全国規模での公益事業活動の核となる2025JAIFA年次大会の開催の取り組み 企画
年次大会は、2025年度、香川県での大会に臨む準備を進めていく。
開催地:香川県高松市 香川県立アリーナ(あなぶきアリーナ)
開催日:5月30日(金)
内 容:公益社団法人としての役割も重視して、一般消費者の方々が参加しやすく魅力あるものとする。 -
11. 2026JAIFA年次大会(開催地:大阪) 企画
第23回目となる開催に向けて、本委員会と開催地の代表者で構成された実行委員会を設置し2026JAIFA年次大会に向けての、企画、運営、動員に携わる。
-
12. 2027JAIFA年次大会(開催地:埼玉) 企画
第24回目となる開催に向けて、本委員会と開催地の代表者で構成された実行委員会を設置し2027JAIFA年次大会に向けての、企画、運営、動員に携わる。
-
13. 2028年度以降のJAIFA年次大会の検討 企画
2028年度以降の大会開催地が決定していない状況にある。JAIFAの大会は、動員規模が大きいこともあり、場所も限定されてくるため、2028年度以降の大会開催地を早急に決定し、会場を確保しつつ、当該ブロック、開催地方協会とも連携が取れるよう検討していく。
Ⅱ.ボランティアおよびエコ活動事業(公益目的事業2)
JAIFAの社会貢献活動は、4万名の会員の組織力をもって、突発的大災害をはじめ高齢者への支援から始まり、今日では、「未来ある子どもたちのために」とした児童支援へと広がりをもって活動を続けてきた。
また、社会貢献活動は寄附だけでなく「いま、私たちが出来ること」の思いをボランティア活動に取り入れて展開してきた。
令和7年度の社会貢献委員会は、公益事業の軸とする「愛のドリーム募金」の事業を引き続き継続させるとともに、「かけがえのない生命とその生命を育んでいる地球環境の保護」のため「タッチ エコ!」のスローガンのもと、エコの視点を取り入れた社会貢献活動も引き続き行っていく。
-
1. 募金等の事業活動の展開 社会
愛のドリーム募金
平成7年から基幹社会貢献事業の位置づけで積極的に取り組んできた愛のドリーム募金活動は、高齢者への支援である「愛のドリーム号」の事業に加えて、未来を担う子供たちへの支援へも拡大し、児童養護福祉施設などへ必要物品等を贈呈してきた。
さらに「愛のドリーム募金」の拡充と活動の周知をはかるため、令和元年度に続き、今後毎年度「生命保険の日(1月31日)」にあわせて「愛のドリーム募金贈呈式」を全国54地方協会が一斉に挙行していく活動とした。「愛のドリーム募金“1月31日生命保険の日”全国一斉贈呈式」 実施方針
・生命保険の日である1月31日を毎年恒例の「愛のドリーム募金贈呈式」とする。
・贈呈式の記録を撮り、年次大会の社会貢献活動報告にて活用できるようにする。
・贈呈先、贈呈品については地方協会が地域の要望に応えて対応する。
-
2. 会員以外の方々と共に協力して参加する体験型「社会貢献活動」の実施 社会
(1) 各種団体が主催する活動への参加
社会貢献委員会は、広報、教育部会等と連携して、広報誌「Present」やホームページに各種団体イベント情報やJAIFAの参加取組情報を掲載して周知を図る。
また、下記団体への支援では、ブロックや地方協会が参加できるように、社会貢献委員会としてもフォローしていく。- ①「リレー・フォー・ライフ」への参加を推進する
- ② スペシャルオリンピックス日本への参加を推進する
- ③ あしながPウォーク10への参加を推進する
- ④ がん教育のセミナーに対して積極的に支援する
- ⑤ その他団体等の活動
(2) 人間の未来を確かにする「地球に優しいエコ活動」へ「タッチ エコ!」をスローガンとした取り組み
年次大会へ参加者が多数集まる事を機会と捉え、プリペイドカード類、タオル類の持参協力により収集し、年次大会開催地域の社会福祉協議会などを通じて寄附をして老人ホームや児童養護施設などで役立ててもらうように取組む。また、職場や家庭内でできる「地球温暖化対策」を推進し地球環境の保護へつなげる。
- ① 年次大会向けて、タオル類、子ども向け絵本の収集活動を推進する。
- ② 地球温暖化の身近な施策へ協力する。
(3) 地方協会の地域の特色を活かした独自の社会貢献事業の推進
- ① 「社会福祉協議会」と連携し、施設への慰問やイベント支援を推進する
- ② 各地方協会行事開催時での持ち寄り活動を推進する
- ③ 地域性を活かした地方協会独自の清掃奉仕活動などの取り組みを推進する
-
3. 社会貢献活動の紹介 社会
ブロック、地方協会、個人会員による社会貢献活動の様子を、年次大会、広報誌等で紹介する。
-
4. ハートフルファンデーション委員会との連携 社会
全国各地で頻発する大災害に対して、ハートフルファンデーション委員会と連携し、すみやかな支援を行うことを推進する。
-
5. ハートフルファンデーション事業 ハト
ハートフルファンデーション基金は、平成27年度から会員一人ひとりの年会費に500円が基金に加えられたことで毎年約2,000万円規模の積立となり、万一の突発的災害時にJAIFAらしい活動を行っている。
平成24年のハートフルファンデーション設立から5年間は、突発的災害支援に加え、基金がどのように活かされていくのか、活動の礎にもなるよう「年度ごとの期限を定めた支援」として毎年500万円相当の寄贈も続けてきた。
平成29年度からは「年度ごとの期限を定めた支援」に代わり「未来ある子どもたち」に焦点をあて、継続して支援をしていくことで、更にハートフルファンデーション活動を展開してきた。
さらに令和5年度から、新たな継続支援先として、NPO法人 ジャパンハートを加えた。継続支援実績(平成29年度から)
公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 公益財団法人 メイク・ア・ウイッシュ オブ ジャパン NPO法人 日本ホスピタル・クラウン協会 NPO法人 ジャパンハート(令和5年度から) -
6. 突発的災害への支援活動 ハト
ハートフル・コーディネーター(HC)
- ・全国54地方協会より1名。(任期は、地方協会役員と同様に1期2年。最長3期6年)
- ・現職の幹事・監査役の中から選出する。(会長・相談役は不可)
- ・主な役割
- ① 地方協会または近隣各地域の災害時における情報収集や指令役
- ② 地方協会長やハートフルファンデーション委員会との連携
- ③ ハートフルファンデーションの普及活動
-
7. 「未来ある子どもたち」への支援活動 ハト
「未来ある子どもたち」への支援として、「愛のドリーム募金」が協会活動として地域に根付いた活動と区別する意味もあり、「ハートフルファンデーション」では全国的に活動を展開している団体へ支援してきた。
継続して支援している上記4団体以外の支援先については、地方協会からの支援要請にも対応していく。推薦団体があれば「決定申請書(事前)」に記入の上、事業報告書、過去3年間の財務状況がわかるものを添えて提出してもらい、ハートフルファンデーション委員にて審議・決定する。
Ⅲ.調査・提言事業(その他の事業)
-
1. 広報誌「Present」の制作方針と頒布拡大 教育
公益社団法人としての取り組み強化の一環として、広報誌「Present」の内容は生命保険事業を通じた社会教育としての立場やボランティア事業の情報など公益性の高い記事を多く掲載するような施策を実施していく。
- ① 誌面上にQRコードを掲載して、会員だけではなく一般の読者にも手軽に読んでもらえるようにして、JAIFAへの理解を深めてもらう。また、誌面では掲載できない図表や詳細な説明をホームページに掲載して、情報量を増やし充実した内容とする。
- ② 紙媒体、冊子での発行部数約15,500部のうち、会員配布以外の約2,000部を地方協会による公益活動広報のため使用している。引き続き、QRコードやホームページからも広報誌「Present」が読むことができることをPRしていく。
-
2. 海外協会への協力 企画
JAIFAが協会設立時の手本とし、長きにわたり交流が続いている全米生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会(NAIFA)へ生命保険業界の発展に寄与するために協力していく。
-
3. JAIFAの公益広報活動 広報
- ① 広報部会は、ホームページを一般消費者へ普及させると共に、本部と地方協会とのコミュニケーションツールとしての活用を図る。
- ② JAIFA公式LINEとホームページ上の会員専用サイト「JAIFA学習帖」をより多くの会員が活用できるようアクセス増加へ向けた周知広報を行う。
- ③ 地方協会の幹事会やセミナー等でホームページやJAIFA学習帖、JAIFA公式LINEを周知、活用してもらえるよう徹底する。
- ④ JAIFAの活動内容をPRする動画を積極的に活用し、状況に応じてラインナップのさらなる充実を図る。
-
4. JAIFA紹介パンフレット「Make a future」の活用 広報
「Make a future」は、会員増強に向け新規入会を促進と一般の方々へJAIFAの活動を紹介するため、積極的な使用を推進していく。
-
5. JAIFAロゴマーク・キャラクター 広報
会員にJAIFAロゴマークや団体名、キャラクターを名刺に表記してもらう。
-
6. JAIFAバッチ 広報
JAIFAバッチの刷新は、継続審議とする。
-
7. 地方協会会計管理体制の機能強化と指導 公益
公益社団法人として、透明性、公平性、健全性を保つ運営と、地方協会へのアドバイスを継続していく。
- (1) 本部・地方協会ともに講師へ支払う諸謝金(講演料)の源泉所得税徴収を徹底する。
- (2) 本部は、地方協会が使途目的を明確にし、決定権限規程に基づく決定申請書の事前申請を行うよう指導する。
- (3) 本部・地方協会ともに、次年度へ引き継がれる事業資金を明確にする。
- (4) 本部は、公認会計士の指導に基づいて、地方協会が行う会計監査を指導する。
- (5) 本部は、地方協会の監査役が、事業遂行の確認を徹底するよう指導する。
- (6) 本部は、会費納入管理を徹底し、地方協会管理運営を指導する。
- (7) 本部は、公益社団法人として透明性、公平性、健全性を全地方協会が保つようアドバイスする。
- (8) 本部は、支出にかかる管理費についても経費削減を図るように全地方協会へ指導する。
- (9) 本部は、令和6年度より導入したブロック活動費の新ルールが遵守されているかを検証していく。
- (10) 本部は、令和6年度より導入した地方協会の共益活動費についての新ルール、すなわち「新聞広告掲載費」「年次大会旅費補助」「地方協会自由経費」の3つの項目に関するルールが、各地方協会において遵守されているかを検証していく。
-
8. 組織活動におけるブロック機能強化 公益
- (1) ブロック単位での地方活動の強化
地方協会のみならず、ブロック単位で開催するセミナー、社会貢献活動に対する本部の助成を強化する。 - (2) 地方協会の組織強化支援
地方協会への担当副理事長による訪問等を促進し、組織強化支援にあたる。
また、下記事項についても本部が支援する。
- ・本部は、ブロック・地方協会が開催する公益事業研修へ本部役員講師を派遣する。
- ・本部は、地方事務局体制が強化されるよう支援する。
- ・本部は、組織増強奨励や地域・会社の分会設立奨励を引き続き促進する。
- ・本部は、事業を円滑に推進し組織体制を整える上で、管理システムの構築や地方事務負担の軽減等につながる対応を促進する。
- ・本部は、地方協会、ブロック等で取り組む社会貢献活動を支援する。
- (1) ブロック単位での地方活動の強化
-
9. 2025JAIFA年次統一セミナー 公益
公益総務委員会は、企画運営委員会が中心となって企画し、開催する年次大会事業に対して、広く一般消費者の方々の参加を促進する大会開催へ向けて適切に必要な予算を確保する。
-
10. 広報PRを活用した公益活動の推進 公益
公益総務委員会は、広報部会が公益社団法人として活動するJAIFAの組織や事業活動内容等の広報PRを推進するうえで、適切に必要な予算を確保する。
Ⅳ.管理部門
-
1. JAIFAの公益事業を津々浦々へ伝達するためにも会員増強への取組みは重要である。そのため、JAIFA加入率が全営業職員の20%増(各協会、各ブロック、各社、それぞれ20%増)となるよう会員増強を目指す。 会員
-
2. 組織強化 会員
(1) 会員継続による組織展開の充実
-
① JAIFA年会費納入方法を「本社控除」へ移行
年会費納入は、令和8(2026)年度を目標に、全社本社控除に移行できるよう取り組む。 -
② 年会費期首払いの徹底
JAIFAの年会費納入ルールは、期首(3月31日までに)一括払いとし、5月31日までを猶予期間としている。この年会費納入ルールを再度徹底することで、年会費納入猶予期間が終了するまでに、当該年度の年会費の入金が終了するようにする。なお、毎年の入金サイクルが期首払いになっていない入金は、令和8(2026)年度を目標に期首払いにしていただくよう調整を促す。 -
③ 年会費送金とともに、「会費送金明細書」「会費納入者報告書」の提出を徹底(地方協会 からの年会費送金時の場合)
地方協会が年会費を本部へ送金する際に、「会費送金明細書」と「会費納入者報告書」を提出し、入金情報を本部事務局へ連携することとなっている。この提出がないと、年会費納入者が不明となり、事務処理ができないため、地方協会へ提出の徹底を促す。 -
④ 現金を取り扱わない方法での年会費徴収の徹底
各会社による給与控除や、各地方協会口座への年会費の振込み、口座振替、Web決済などを利用し、年会費やセミナー参加費などについて現金を取扱わないようシステム化する。
(2) 情報共有化の徹底(活動格差の是正)と地方協会の組織力強化
- ① 本部と地方協会が情報を共有できるよう連携の強化をし、地方協会からの情報のフィードバックを得ることにより、各地方協会間での情報・活動の格差の是正を図る。また、委員が各ブロック長や会社代表役員と連絡をとり、会員増強を推進できるよう取り組む。
- ② テレビ会議システムを構築し、旅費等経費の節減を図り会議を合理化する。
(3) 生命保険協会並びに生命保険会社各社等との連携強化
- ① 生命保険各社訪問
- ② 生命保険協会、地方生命保険協会及び公益財団法人生命保険文化センターとの連携強化
-
① JAIFA年会費納入方法を「本社控除」へ移行
-
3. 会員増強策への取り組み 会員
- (1) 会員増強に成功している地方協会、会社の事例について研究し、情報の共有から学び、迅速な実行の推進を図る。
- (2) 会社分会・地方分会の設立の推進と積極的支援を推し進める。
- (3) 新規入会キャンペーンなどを実施する。
- (4) 会社毎の現況を判断しつつ、会員増強の対応を各社事務担当者と会社代表、本部事務局とのコミュニケーションを密にして相互連携により取組む。
-
4. 公益総務委員会は、財務、税制・公益総務という事業を担当するうえで、公益法人としての事業に律する牽引役として活動していく。
特に、財務面では、本部・ブロック・地方協会ともに経費節減と合理化を図り、公益事業に臨む各事業の必要経費を確保するとともに、より有効な運営を目指していく。 公益 -
5. 公益事業比率を高める 公益
本部、9ブロック、54地方協会毎に、事業年度予算で公益事業比率70%以上を達成することを基本としているが、より一層公益性を高めるよう財務面での強化をしていく。
-
6. 事業運営にかかる管理促進 公益
公益総務委員会は、下記事項について担当する委員会・部会が、公益目的事業を効果的かつ安定的に推進できるよう、各事業予算を確保する。
- (1) 教育部会が担当する生命保険の役割や関連する情報を掲載した小冊子の制作と活用事業。
- (2) 公益総務委員会が担当する国民や保険契約者等の保護の観点から、法律や制度上の問題、政策等への提言のために必要となる予算を確保する。
- (3) 会員増強委員会が組織拡充増強に取り組むための必要予算を確保する。
- (4) 公益総務委員会は、本部事務局の会計システムなどの事務局に必要経費を確保する。
-
7. 制度上の問題点に対する取り組み 公益
公益総務委員会は、公益社団法人として活動するうえで、国民や保険契約者等の保護の観点から、法律や制度上の問題点等について、公平な視点に立ち意見を発して取り組む。
特に、税制改正による生命保険料控除制度拡充要望等にあっては、制度改正の動向を注視しつつ必要に応じて意見や要望を提出するなどの対応を行う。 -
8. ディスクロージャー 公益
公益法人は、公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化及び適正化を図るとともに、行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)等に基づく公益法人改革の推進に資するため、各府省(国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ。)は、インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて、必要事項をホームページにて公開することが義務付けられている。この決定に基づき、JAIFAも必要な情報を公開する。
-
9. 公益法人としてのさらなる体制強化を図る 公益
(1) 公益法人は、不特定多数の方々の利益の増進に資するよう、新たに作られた厳格な基準が課されている(認定法第5条)。大きく分けると、①公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準と、②公益目的事業を行う能力・体制があるかという「ガバナンス」の基準とがある。
公益社団法人としてのJAIFAは、本部・9ブロック・54地方協会が一元化した組織と運営体制をもって構成されている。組織の原点をもう一度認識し、公益法人としてさらなる体制強化を図る。
また、コンプライアンス室と連携し、事務運営に内部けん制を意識してチェック体制をとるとともに、内部統制を強化する。(2) 委員会の横連携
各委員会や部会が活発に事業展開するうえで、相互に関連する事業項目については、委員会の横連携をもって、より効果的に成果をあげられるように取り組む。